Cross Talk _ 002
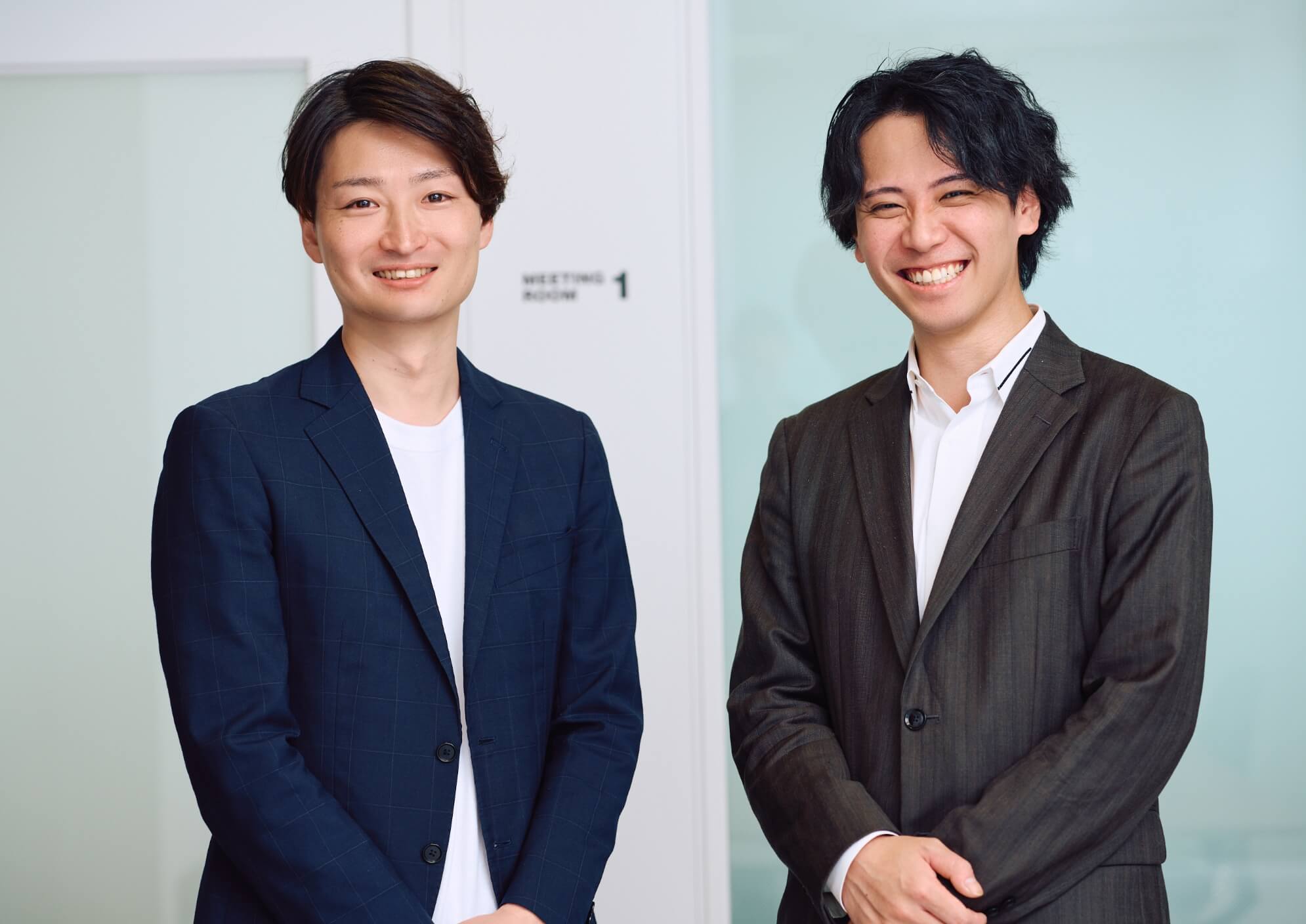
Cross Talk _ 002
信頼される理由は、
細部への執念と、
チームの挑戦心。
細部への執念と、
チームの挑戦心。
マネージャー
大野 崇人
Shuto Ohno
マネージャー
久保 翔
Sho Kubo
Profile
-
 マネージャー大野 崇人Shuto Ohno新卒で株式会社エイチ・アイ・エスの法人営業本部に入社し、自社の業務改善や利益率向上に貢献し本部長賞を2回受賞。
マネージャー大野 崇人Shuto Ohno新卒で株式会社エイチ・アイ・エスの法人営業本部に入社し、自社の業務改善や利益率向上に貢献し本部長賞を2回受賞。
その後株式会社オンリーストーリーに転職し、入社5ヶ月でトップセールスとなる。
同年ベストセールス賞を受賞後、セールス責任者に就任し、2年半の在籍で約1,000回の決裁者商談を行った。
DeCoA入社後は、独自のリサーチ手法によるマーケティング戦略の策定から施策実行の伴走型支援を担当。 -
 マネージャー久保 翔Sho Kubo大手生命保険会社にて、生命保険などの金融商品の販売をはじめ、顧客のライフスタイルに応えるソリューション営業に従事。全国同期 2,000人の中で件数・料額ともに一位を獲得。その後、製造系ベンチャー企業の営業マネージャーとして、全国最下位の部署の売上を全国 TOP・昨対では 215%まで引き上げ、リブ・コンサルティングに入社。営業強化支援・WEB マーケ支援などさまざまな支援を行い、社内賞を複数受賞。現在は DeCoA のマネージャーとして、住宅不動産・メーカー・パーソナルジム・アパレル・美容室・塾など多岐にわたるクライアントを支援し、トップライン向上において戦略構築~伴走支援を行っている。
マネージャー久保 翔Sho Kubo大手生命保険会社にて、生命保険などの金融商品の販売をはじめ、顧客のライフスタイルに応えるソリューション営業に従事。全国同期 2,000人の中で件数・料額ともに一位を獲得。その後、製造系ベンチャー企業の営業マネージャーとして、全国最下位の部署の売上を全国 TOP・昨対では 215%まで引き上げ、リブ・コンサルティングに入社。営業強化支援・WEB マーケ支援などさまざまな支援を行い、社内賞を複数受賞。現在は DeCoA のマネージャーとして、住宅不動産・メーカー・パーソナルジム・アパレル・美容室・塾など多岐にわたるクライアントを支援し、トップライン向上において戦略構築~伴走支援を行っている。
Talk Theme
「そこまでやる」の実践と、
これからの提供価値とは。
妥協せずに提案を磨き上げる姿勢。経営者視点で支援の価値を見極める目線。そして、チームの知見を横断的に活用しながら、期待を超えるアウトプットを追い求める日々。現場の第一線で支援をリードするマネージャー陣のお二人が、DeCoAにおける“プロフェッショナリズム”のリアルを語ります。

当たり前の基準が高いんだと思う。
妥協がないからこそ、信頼につながっている。
妥協がないからこそ、信頼につながっている。
普段「そこまでやるか」を意識する場面というのは。

久保
「そこまでやるか」を意識する場面って、大きく2つあると思っていて。ひとつは社内的なところ、もうひとつはクライアント向きの姿勢ですね。
まず社内でいうと、僕の前職だとMTGまでのスケジュールは、「◯日前にチェック」みたいなフロー通りに進めることが多かったんです。私はだいたい3日前には資料を仕上げていました。でもDeCoAは、計画的にスケジュール通りに進めるものの、提案ギリギリまで粘る。直前まで見直して何度もロープレをして、「もう1文字でも良くしたい」っていうブラッシュアップを、みんなが当然のようにやってるんですよね。この「妥協しない仕上げ方」には、社内カルチャーとしての“そこまでやるか”を感じますね。
まず社内でいうと、僕の前職だとMTGまでのスケジュールは、「◯日前にチェック」みたいなフロー通りに進めることが多かったんです。私はだいたい3日前には資料を仕上げていました。でもDeCoAは、計画的にスケジュール通りに進めるものの、提案ギリギリまで粘る。直前まで見直して何度もロープレをして、「もう1文字でも良くしたい」っていうブラッシュアップを、みんなが当然のようにやってるんですよね。この「妥協しない仕上げ方」には、社内カルチャーとしての“そこまでやるか”を感じますね。

大野
中途半端なアウトプットを出すくらいなら、出さない方がまし、みたいな空気は、たしかにありますよね。


久保
ですよね。もうひとつのクライアント側で言うと、DeCoAのメンバーって「この支援、自分が相手の会社の社長の立場だったらどう見えるか?」みたいな想像力をすごく働かせるんですよ。単に“課題を解く”だけじゃなくて、「経営者がこれを見てどう思うか?」まで想定して、支援の質を突き詰める。

大野
ああ、わかります。僕も入社してすぐ、当時のマネージャーから「大野さんがこの会社の社長だったら、どうします?」って何度も聞かれたな。

久保
でも、それがDeCoAのベースになってますよね。「働くこと自体が価値」って考える人もいるけど、うちは「価値を出すために働く」っていう姿勢の人が多い。だから、自分の時間をどう使ってでも、価値を出し切る。
たとえば、同じ8時間働いたとしても、それが“どれだけの価値に変換されたか”にこだわるというか。
たとえば、同じ8時間働いたとしても、それが“どれだけの価値に変換されたか”にこだわるというか。

大野
たしかにそうですね。時間をかけることに満足する人って、あまりいないかもしれない。

久保
そうなんですよね。8時間でこれ、って満足するんじゃなくて、「もっと短時間で高い価値を出せるように鍛える」っていう感覚。

大野
その延長で言うと、アウトプットの中身はもちろん、伝え方や見せ方へのこだわりもすごいですよね。どんな資料にまとめるか、どう見せれば刺さるか。全部含めて「支援の質」だと考えている。クライアントワーク経験豊富な人でも、最初は詰まる部分ありますもんね。

久保
ああ、いますね。「事業責任者やってました!」みたいな人でも、「このまとめ方は違う」とか「伝え方が弱い」とか、言われる場面って結構ある。

大野
そうそう。それぐらい、当たり前の基準が高いんだと思う。
妥協がないからこそ、信頼されるんですよね。
妥協がないからこそ、信頼されるんですよね。
論理性、フィジビリは当たり前。
「ワクワクできるかどうか」を、いかに詰められるか。
「ワクワクできるかどうか」を、いかに詰められるか。
DeCoA流のプロフェッショナリズムとは何なのでしょう。

久保
DeCoA流のプロフェッショナリズムって、言葉で言うといろいろありますけど、私は大きく3つの視点があると思っていて。ひとつは論理性、ふたつ目が現実性、そして最後が期待感——「ワクワク」です。

大野
うんうん、わかります。僕もまずは「意思決定の材料をそろえる」っていうのが前提かなと。お客さんが「やりたい」と思えるかどうか。やる理由が腹落ちするかどうか。それってロジックだけじゃなくて、安心できるとか、ワクワクできるとか、気持ちの部分も含めての話なんですよね。

久保
そうですよね。論理性があるっていうのは、「このロジックで進めば、きっと成果が出る」っていう納得感を作れること。現実性は、ちゃんと体制やスキルが揃っていて「実行可能ですよ」と言えること。そして期待感は、「この提案、やったら面白そう!」ってワクワクさせられるかどうか。


大野
その“ワクワク”が一番むずかしい。実際に「論理もあるし、実現性もある。でもワクワクしない」って代表の吉松さんから言われること、ありますよね。

久保
ありますね。そこを超えて、「これって、ウチの理念にも通じるし、未来が広がるかも」って思ってもらえるか。私たちがどれだけ相手の期待を超えられるか、視座を引き上げられるかが、プロとしての勝負どころだと思ってます。

大野
施策にワクワクしてほしいからこそ、資料のクオリティも最後の最後まで粘るんですよね。ロジックが通ってるか、ストーリーが逸れてないか、図解ひとつ、言葉ひとつまで、直前まで何度も何度も見直す。

久保
プレゼンの前とか、めちゃくちゃセルフロープレしますよね。

大野
しますします。「ここ、もう1トーン上げて言おう」とか「図の順番逆にした方が伝わるな」とか。そういう細かい修正の積み重ねも、提案する施策に納得してもらうため・ワクワクしてもらために重要だと思います。

クロスイノベーションが生まれやすい土壌。
そこから、もっと大きな “一打” を狙いたい。
そこから、もっと大きな “一打” を狙いたい。
今後さらに顧客価値を高めていくための「そこまでやるか」は?

久保
私が思うDeCoAにしかない最大の顧客価値って、「クロスイノベーションの発想が生まれる環境」なんです。業界や企業規模を問わず、多様な案件に関わってきたメンバーが集まっているからこそ、「他業界でうまくいったやり方を、自分たちに応用できないか?」という視点が自然と出てくるんですよね。

大野
そうですね。僕らも事例を出すとき、同じ業種・業界から引っ張ってくるというよりは、「この課題、別の業界でも似たケースがあって、こう解決しましたよ」っていう切り口の方が多いかもしれません。

久保
それって、本質的な課題に向き合ってるからこそだと思っていて。たとえば大企業で導入されてる仕組みを、そのまま中小企業でやるのは難しくても、スモールサイズに落とし込んで提案する、みたいな工夫ができるんですよね。


大野
DeCoAとしても、そうした引き出しを増やすために「顧客数を増やす」というのを大きなKPIに置いていますからね。案件のバリエーションが広がるほど、提案の選択肢も広がる。それが結果的に顧客価値の向上につながるという考え方。

久保
社内の体制も大きいですよね。誰が誰にレビューを飛ばしてもいい。私から大野さんにすることもあれば、大野さんのチームに私からレビューすることもあるアットホームさもあるし、それぞれが「その人だけの強み」を持ち寄る“集合天才”みたいな面もあると思います。たとえば大野さんなら、経営者とのネットワークや交流会で得た知見が豊富で、それが提案の幅を広げたりする。そうした一人ひとりの知見や得意領域を社内でフル活用できるからこそ、クライアントに提供できる価値も格段に高くなると感じています。

大野
そうですね。僕も久保さんが進めている代理店営業系の案件、スプレッドシートをこっそり参考にさせてもらったりしてます(笑)。そうやって社内の知見を横展開しながら、クライアントごとの最適解を探っていくのが、DeCoAらしさかなと。

久保
それこそ、「誰かが持っている得意分野」をクライアントに還元する構造が自然にできている。その点でも、DeCoA全体として“そこまでやるか”を体現できている気がします。

大野
個人の挑戦としても、やっぱり“代表作”みたいなホームランを何本か出していきたい気持ちはありますね。それが結果的に他の案件にも転用できて、また別のクライアントへの提供価値になる。そういう成功体験の連鎖を作っていけたらと思っています。
自分の強みを武器に、
思い切って飛び込んできてほしい。
思い切って飛び込んできてほしい。
ちなみに、お二人がジョインした時の第一印象は?

大野
僕は、いい意味で「これまでの常識が通用しないな」と思いました(笑)。当時はまだ人数も少なくて試行錯誤もあって、やってることも結構独特で。正直、最初はちょっと驚きましたね。

久保
わかります、それ。私も面接の時のロジカルな印象と、現場のラフさにギャップを感じたんですよね。

大野
そうそう。でも、それが逆に「ここでやれば、自分の幅が広がるかも」って思えるところでもあって。

久保
まさに。代表とのやりとりやプロジェクトを通じて、「本質を突いてる会社だな」ってどんどん印象が変わっていって、愛が強くなりましたね。

最後に、求職者へのメッセージをお願いします。

久保
私のチームでは、最初に必ず「あなたの人生の目標は何ですか?」と聞くようにしています。その目標を実現するために、1年後の理想像を描き、今どんなスキルを身につけるべきか、どんなプロジェクトに挑むべきかを一緒に設計するんです。そして、「この人はこういう未来を描いているからこのプロジェクトに入ってもらおう」「この経験を通じてこの力をつけてもらおう」と意図を持って仕事をアサインしています。

大野
僕も、マネージャーとして、メンバーのキャリアビジョンを聞きながら「得意を活かす業務」と「チャレンジングな領域」の両方をバランスよく渡せるようにしています。DeCoAは「勉強しに来る」ことが許される、というよりむしろ歓迎される会社だと思いますね。

久保
DeCoAを通じて人生の目的を達成してほしいし、たとえ卒業する時が来ても「この会社で成長できてよかった」と思える時間にしてほしい。それが私たちのチームのあり方です。自分でアウトプットしながらも学びたい──そんな意欲がある方には、きっとぴったりの環境だと思います。

大野
特に最近は、何かひとつでも「ここだけは自信がある」と言える領域を持っている方に加わってほしいと思っています。逆に、それ以外の部分は僕らやチームでいくらでもカバーできる。だからこそ、自分の強みを武器に、思い切って飛び込んできてほしいですね。



